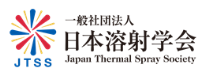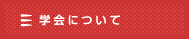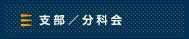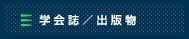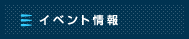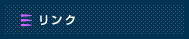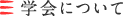会長あいさつ
会長就任のご挨拶

日本溶射学会の皆様,このたび,第41期会長を拝命いたしました東京都立大学の髙橋 智です.これまで,榊 和彦元会長,小川和洋前会長のもと,副会長(内務担当)として,多くのことを学ぶ機会に恵まれました.特に第40期では,小川前会長が強いリーダーシップでアジア溶射会議(ATSC2024)を進め,学会として大成功を収めることができました.この流れを第41期にも活かし,微力ながら学会のさらなる発展に貢献できるように尽力して参ります.
日本溶射学会は,溶射に関する理論および工業の発展を図ることを目的に1957年に設立され,2027年には70周年を迎えます.学会パンフレットには,“当学会は,溶射技術のさらなる革新と普及に向けて研究者・技術者が集い,共に切磋琢磨し国際的ネットワークを構築する場を提供します”と明記されております.諸先輩方の当学会及び溶射に対する熱い思いを改めて確認するとともに,引き継いでいきたいと存じます.
さて昨今の社会状況は,“2050年カーボンニュートラル宣言”,“GX(グリーントラスフォーメーション)”,“カーボンプライシング構想”,“DX(デジタルトランスフォーメーション),”サーキュラーエコノミー“,”労働人口の減少“などのキーワードが挙げられるように,大きく変化しております.一方,溶射技術は,産業機械,インフラ,エネルギー・プラント,半導体,自動車,航空機,医療など様々な分野で適用されている反面,次の課題が挙げられます.”溶射材料の歩留まりが悪くて,コスト高“,”ガス・酸素の大量消費“,”溶射の技術者不足,技術の継承“,”溶射技術開発力の低下“,”新たなアプリケーションが生まれない“などです.さらに学会においても,”会員数や溶射研究者の減少“,”講演発表や投稿論文の減少“,”各委員会における委員の負担増“などの課題が深刻化しております.したがって,社会状況に対応した研究開発に取り組み,学会活動を活性化させ,溶射産業に貢献することが求められております.
このような状況を踏まえ,第41期では,『溶射技術の新たな可能性の探求と溶射産業の発展への貢献』をスローガンとして,1) 研究活動の活性化,2) 人材育成,3) 学会運営の改善に取り組みます.まず研究活動の活性化として,次の3つの研究分科会を立ち上げます.すなわち,①「皮膜強度」研究分科会(主査:小川和洋氏),②「AI技術活用」研究分科会(主査:渡邊 誠氏),③「溶射プロセスにおけるライフサイクル環境負荷評価」研究分科会(主査:和田国彦氏)です.多くの会員の皆様にご参加いただき,一緒に溶射技術の新たな可能性を探求したいと考えております.さらに国研・公的研究機関との連携によるものづくり研究の促進,日本溶射工業会との連携による研究実施,若手研究者らの研究活動支援にも取り組みます.次に人材育成として,溶射講習会や基礎セミナーなどを企画・開催するとともに,将来の溶射技術者の育成を目指して東南アジアなどとの交流促進も図っていく所存です.そして学会運営の改善として,委員会活動の効率化,学会活動の積極的な情報発信(HPのリニューアル),支部活動の活性化,財政の健全化,フェローやシニア会員制度の導入も推進する所存です.
以上,会員の皆様に有益でかつ楽しい場を提供できるように,理事会,各委員会,各支部,事務局と連携しながら,学会活動に取り組んで参りますので,会員の皆様のご理解とご協力を切にお願いし申し上げます.